ぱぱネット(仮)
2008-10-30 秋の夜長の楽しみ [長年日記]
_ [PC] D945GCLF2を購入
これインテル純正の デュアルコアAtomマザーボード。MiniITXというフォームファクタで、 CPUが直付けされているものの、1万円以下という価格が魅力。
俺は、5年以上前にVIAのEPIA C3マザーに Procase2というケースで、ファンレスPCを組んだことがあるのだが、さすがに現代ではWebを見るにも辛い性能で(※動画はおろかフラッシュがまともに再生できない、と言えば伝わるだろうか)、完全に物置の肥やしになっていた。これを今回は救おうというお話。
_ Procase2で組み上げてみると・・・
・・・・あれ?!
EPIA C3にはなかった背高の音声出力端子がProcase2のPCIスロットと干渉する。なんでケース側に余計な出っ張りが!
しょうがないので、もう一台余っていた窒息ケース OWL-PCBM-01に乗り換え。

|
_ 電源の移設
しかしトータルで45Wしか食わないシステムに、300WのSFX電源は如何にも無粋。そこでProcase2のACアダプタ電源基板を移植した。DC-DCコンバータは片側ネジ止め、もう片方はちゅうぶらりんなのでプラ板で支えを自作。

|
さらにACアダプタはケースファンを取り外したメッシュを貫通させるように配置した。固定はシリコンワッシャーにタッピングネジで。

|
これでSFX電源は完全に停止、上部に6cm/1000rpmの静音ファンを設置して、静音化は完璧。と思ったら
もう少し低回転でまわせないものかインテル。安いファンコンないかな。
_ OSはUbuntu
世間では評判の良い Ubuntu Linuxをインストールしてみた。 VIA C3からの乗り換えで、図らずもシングルスケーラCPU同士を比較するハメになったわけだが、 言うまでもなくAtomの圧勝 という感じ。 しかしAthlon64あたりと比較するとずいぶん遅いのもわかる。特にコンパイルするとね。でも全然許容範囲。

|
CPUはデュアルコアだが、1コのAtomコアがSMT(いわゆるハイパースレッディング)をサポートするので、OSからは4コアに見える。言わばなんちゃってクァッドコアプラットホーム。
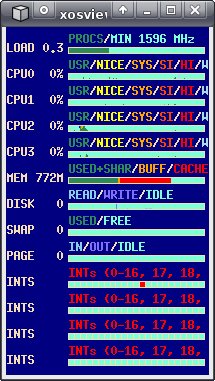
|
_ しかし大問題発生
Ubuntu、Debian系だと聞いていたから安心していたんだが、
ここ30年。UNIX OSが起動する際には、どのプラットホームでも 真っ先に起動していたinit。こいつでさえUbuntuではお役御免なのか?! 神は死んだ! (言いすぎ) というか慣れた方法で起動制御できないと激しく困るんだが。 どうしたもんか。どーも調べると Upstartというinitに変わる初期化プロセスに変えたから、 起動が速いってことらしいんだけど。
さて・・・DebianかVineに入れなおすかな(←軟弱モノ)
- https://www.google.co.jp/ ×11
- http://www.so-net.ne.jp/search/web/?latest=all&yur... ×3
- http://www.google.com/reader/view/ ×2
- http://www.google.com/search ×2
- https://www.google.com/ ×2
- http://www.google.co.jp/cse?cx=partner-pub-6078229... ×2
- http://www.google.co.jp/cse?cx=partner-pub-6078229... ×2
- http://kreisel.fam.cx/webmaster/mugen/kamado-n-200... ×2
- http://www.google.co.jp/reader/view/ ×1
- http://www.google.co.jp/reader/view/user/180493167... ×1
- http://www.google.co.jp/reader/view/?hl=ja&utm_sou... ×1
- http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.pap... ×1
- http://www.google.co.jp/linux?hl=ja&q=ファンレス マザーボード... ×1
- http://www.google.co.jp/cse?cx=partner-pub-6078229... ×1
- http://www.google.co.jp/cse?cx=partner-pub-6078229... ×1
- http://www.google.co.jp/cse?cx=partner-pub-6078229... ×1
- http://www.google.co.jp/cse?cx=partner-pub-6078229... ×1
- http://www.google.co.jp/cse?cx=partner-pub-6078229... ×1
- http://www.google.co.jp/cse?cx=partner-pub-6078229... ×1
- http://www.google.co.jp/ ×1
- Yahoo検索(�N�@�b�h�R�A) ×1
- http://search.manpukujima.com/?Keywords=�ǥ奢�륳�� Ub... ×1
- http://fieldnotes.sytes.net/soleil/view/index.html... ×1
![[BANNER]](../image/banner.png)
このサーバーをもう12年も維持しているかと思うとめまいがしますよ。
ツッコミ機能は、ハンドル名が完全日本語じゃないと登録できません。
また、本文にURLが含まれていても登録できません。
いずれもSPAM対策です。
![[Panda Papanda]](../image/panda.jpg)
|
訪問者数:(11777+2560143)
- 2008-10-31
- こともなし
- 2008-10-30
- D945GCLF2を購入
- Procase2で組み上げてみると・・・
- 電源の移設
- OSはUbuntu
- しかし大問題発生
- 2008-10-28
- 何の前触れもなく
- ふとぱぱサーバのことを想う
- 2008-10-27
- 昔からおかしかったんだがね
- そして日本の台所から
- 2008-10-26
- 気圧の関係なのかなんなのか・・・
- 夕食ピーマン
- 2008-10-25
- まずそうなものはまずそう
- 2008-10-21
- ともりん先生のスキャナ
- 2008-10-20
- ブレブレブレブレ・・・
- 過去に学べ
- 2008-10-19
- 納入日
- ああ、運命の・・・?f100d
- チネチッタPIZZA SALVATORE CUOMO & GRILL
- が、やはりGUIはダメだ
- 作例
- うーむ
- 2008-10-17
- 問いかけ
- いかんいかん!
- 2008-10-13
- ここまで違うのか
- しかし鉄ちゃんと違って
- 悩む
- もういいかげん決めたいのだが
- 2008-10-09
- 多すぎて訳がわからない〜(笑)
- この取り残され感っ...
- 2008-10-08
- バナナが山盛り積んであった
- ポイントは「記号化」か
- ダイエットに効くテレビ
- そういう俺は
- 2008-10-07
- ボケ過ぎている
- それだけかけるなら俺的には...
- 事業者ならば....
- 2008-10-04
- ともりん先生すみません
- パンチェッタ
- 2008-10-03
- 電子技術の祭典CEATEC
- 今年はおとなしい展示が多いな
- しかしCEATEC自体は大盛況か
- ハプニング
- 2008-10-02
- またWindows Vistaの文句ですよっと
- MS Windows Defender
- こんなものが公然と売られている
- ...と思ったのだが
ぜひ、Ubuntuをしばらく使いこんで頂きたいかと。
特にUbuntuではGNOME周りが、これ作ったのMicrosoftだろう?って思える位、訳の分からん動作するし、全然枯れとらんです。たぶん、LinuxをつぶすためにMSより送り込まれた刺客ですよ。
inittabなんてinitの歴史から見たら新しいですよ。Linux系OSだって初期にはBSD系init使ってましたから、inittabなかったはずです。
/etc/inittabないですが、手で書いてしまえば勝手に読み取るようになっています。 >upstart
きゃあああ誰も読んでないと思ってテケト〜なこと書いてたら突っ込みがはいってるううう(笑)